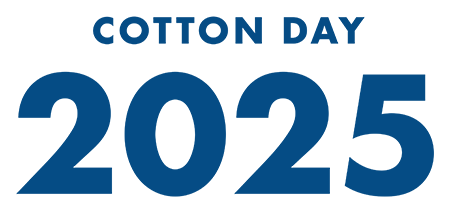
| 一般財団法人日本綿業振興会 |
「5月10日は、コットンの日」
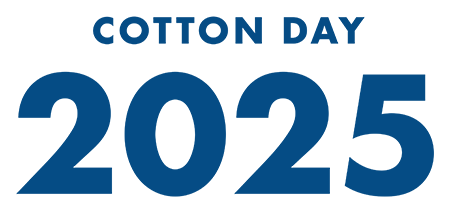
日本紡績協会と一般財団法人日本綿業振興会は国際綿花評議会(CCI)、コットン・インコーポレイテッドの協力を得て、2025年5月9日(金)にホテル雅叙園東京で208名の業界関係者をお迎えし、コットンの日記念イベント「コットンの日2025」を開催しました。 「コットンの日」は1995年に日本紡績協会が国産綿製品需要振興活動を行う上で、夏物綿製品が一斉に店頭に並び始める時期であることと、5(ご)と10(とお)の語呂合わせから、5月10日を「コットンの日」にすることを提唱し、日本記念日協会から正式に認定を受けて制定された記念日です。 30周年の節目を迎えた今回のイベントでは、「Expanding Beyond Borders ― 国境を超えた成長へ」をテーマに、欧米市場に精通された専門家の方々をお招きし、データや法令、時流などの視点から海外市場でのビジネスチャンスを見出すためのセミナーを開催。さらに、「COTTON AWARD 2025」の授与式も実施され、新緑の季節にふさわしく活気にあふれたイベントとなりました。
|
| 尻家正博 日本紡績協会会長よりご挨拶 |
 |
| 国産綿素材の需要促進を目的として、1995年に5月10日を「コットンの日」と定め、本年でちょうど30年という大きな節目を迎えることができました。本来、「コットンの日」は5月10日ですが、本年はその日が土曜日にあたるため、一足早く本日イベントを開催する運びとなり、本年もアメリカ綿花業界を代表するCCI国際綿花評議会ならびにコットン・インコーポレイテッドのご支援を賜り、ここ東京にてイベントを開催できますことを、大変嬉しく思います。 さて、昨今の日本の繊維業界に目を向けますと、円安を追い風にインバウンド需要の回復もあり、一部のアパレルや小売業界では明るい兆しが見え始めています。一方で、人口減少や少子高齢化といった構造的な課題により、国内市場は引き続き縮小傾向にあります。 こうした状況を踏まえ、我々が持続的な成長を実現するためには、視野を世界に広げ、海外市場への展開をより一層加速させていくことが重要であると認識しております。そのような思いを込めて、今年のコットンの日のイベントテーマは「Expanding Beyond Borders ― 国境を超えた成長へ」と掲げました。 本日は、欧米市場に精通した専門家の方々をお招きし、大変有意義なご講演を予定しております。皆さまの今後の事業展開に少しでもお役立ていただければ幸いです。 また、当協会の関係団体である日本綿業振興会では、本イベントの開催に加え、国産綿素材の魅力をより多くの方々に知っていただけるよう、さまざまなプロモーション活動を展開しております。今年も全国紙を活用した広告を通じて、消費者への認知向上に努めてまいります。引き続き、皆さまからの温かいご支援とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 |
| 特別講演 | ||
| 「欧州連合の政策動向:コットン・サプライチェーンへの影響」 | ||
| ヒルアンドノウルトン アカウント・ディレクター マルタ・ボンベーリ 氏
|
||
| ▼▼▼▼▼▼ | ||
| ■サプライチェーンに影響を与える重要な5つの法案 | ||
|
欧州連合(EU)は現在、持続可能性に関する法整備を急速に進めており、とくに繊維業界、そしてコットン・サプライチェーンに対して大きな影響を与えています。今回の講演ではその中でも特に重要な5つの法案に焦点を当てて説明します。 それでは各法案の詳細に進む前に、EUにおける立法プロセスを簡単にご説明します。まず、EUの行政執行機関である欧州委員会が立法提案を行い、その後、欧州議会とEU理事会という二つの主要な機関に提案が送られます。 欧州議会は、各国の人口比に基づいて直接選挙で選ばれた代表から構成され、国別ではなく政治的イデオロギーに基づくグループに分かれています。一方、EU理事会(カウンシル)は、EU加盟27か国の政府を代表しています。この二つの機関は、それぞれ修正案を提出し、欧州委員会、欧州議会、EU理事会の三者が交渉を行う「三者対話(トリローグ)」と呼ばれるプロセスを経て最終的な法案を決定します。合意に至るまでの期間は通常3〜6ヶ月程度ですが、場合によっては合意に至らず、提案が差し戻されたり、合意までに何年もかかることがあります。そのため、法案に関する情報を得た場合は、今、どのプロセスなのかを意識し、合意内容が変わる可能性も視野に入れておくことが重要です。 |
||
| ■企業にサステナブルな取り組み義務付ける「CSDDD」と「CSRD」 | ||
|
最初に取り上げる主要なEUの政策案は、「企業持続可能性デューデリジェンス指令(CSDDD)」と「企業持続可能性報告指令(CSRD)」の2つです。この2つは密接に関連しており、CSDDDは企業に対して環境的・社会的責任を果たすことを求め、CSRDはその責任の履行状況について透明性をもって報告することを義務づけるものです。これらの法案は持続可能性に関する要件が複雑すぎるため批判が高まっていたのですが、2025年2月、欧州委員会は企業の負担を軽減しつつ、実効性を高めるために一連のルール見直した『簡素化パッケージ』を打ち出しています。 それではCSDDDについて詳しく説明します。この指令では、企業が自社だけでなく、サプライチェーン全体に対しても責任を持つことが求められます。たとえば、環境破壊や人権侵害などのリスクを未然に防ぎ、必要に応じて是正措置を講じることが義務づけられます。企業は苦情受付の仕組みを整備し、関連情報を適切に開示する必要があります。また、5年に1度はサプライチェーン全体を評価し、重大な違反が確認された場合には、該当サプライヤーとの契約を停止する措置も求められます。これにより、企業にはこれまで以上にサプライチェーンのトレーサビリティ(追跡可能性)を確保する責任が生じ、データの把握やサプライヤーからの情報収集が極めて重要になります。 このCSDDDは、2028年からEU域内外の企業に適用される見込みですが、これはまだ最終決定ではなく、今後の法的手続きを経て正式な合意に至る必要があります。適用対象は主に大企業であり、企業は「ダブルマテリアリティ(両面の重要性)」の考え方に基づき、自社の事業活動が環境や社会に与える影響と、環境・社会の変化が企業活動に与える影響の両方を評価し、対応することが求められます。 続いてCSRDについて見ていきます。この報告指令では、企業が自身の持続可能性に関する取り組みやリスクを、透明かつ一貫性のある方法で報告することが求められます。そのための基準として、欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)が用意されています。ESRSは、業種を問わない共通のフレームワークとして、気候変動、生物多様性、労働者の権利、地域社会、企業統治といった幅広いテーマをカバーしています。 企業にとって重要なのは、このCSRDにどのように対応すべきか、どの報告基準に準拠する必要があるのかを、今の段階から正しく理解し、準備を進めることです。CSRDとCSDDDの双方が企業に求める要件は多岐にわたり、従来よりも一層高度な対応が必要とされるため、早めの情報収集と体制整備が不可欠です。 |
||
| ■3つの法案で製品づくりから消費までを規制 | ||
|
製品表示および消費者向けの市場規制に関する法案に移ります。ここでは、「持続可能な製品のためのエコデザイン規則(ESPR)」、「製品表示規則」、「グリーンクレーム指令」という3つの法案をご紹介します。 ESPRは、2024年7月に施行された規則で、製品の設計段階からサステナビリティを考慮することを目的としています。特に、エネルギー効率、カーボンフットプリント、リサイクル素材の含有量、製品の耐久性、再利用性、アップグレード可能性などが要件として含まれており、企業はこれらの情報を製品に関して開示する義務があります。また、この規則では「デジタル製品パスポート」の導入も義務付けられており、製品ごとのIDとしてサステナビリティに関する情報を消費者に提供する役割を果たします。 繊維製品はこのESPRの中でも特に優先度の高い製品カテゴリとされており、2026年に草案が作成され、2028年初頭から適用が開始される可能性があります。 次に、「製品表示規則」についてですが、これは2011年から施行されている既存の規則を改正するものであり、特に繊維の素材、手入れ方法、燃焼性に関する情報を標準化して提供することが目指されています。現在は初期段階にあり、レビューや提案の詳細は未発表ですが、デジタルラベルの導入など新たな要件が含まれる可能性があります。欧州委員会は、2025年第3四半期に草案を発表し、最も早くて2028年以降に適用が開始される見込みです。デジタル製品パスポートとの連携も重視されており、両者は緊密に関連して進められています。 最後に取り上げるのは、「グリーンクレーム指令(Green Claims Directive)」です。「グリーンクレーム指令」とは、製品に関する環境表示の信頼性を高めることを目的としたEUの新たな規制です。この指令は、企業が消費者に対して環境に関する主張を行う際に、それが科学的に裏付けられたものであることを義務づけるものであり、いわばグリーンな製品表示における“最低限のルール”を定めたものです。 たとえば、ある製品が環境に与える影響や性能について、企業が「エコ」や「持続可能」といった主張を行う場合には、それが製品全体に関するものなのか、あるいは一部の特定要素に関するものなのかを明確にする必要があります。さらに、その主張が製品のライフサイクル全体の中でどの段階に関連するのか、また他の側面との相関があるのかについても説明しなければなりません。 このような主張を行う際には、確かな科学的根拠に基づく証拠(エビデンス)を示すことが求められます。そして、そのエビデンスは独立した第三者機関によって検証される必要があり、検証に合格した場合には、指令の要件を満たしていることを証明する「適合証明書」が発行されます。 なお、EUエコラベルのように既存の認証制度によって適正に表示されている場合には、あらためて本指令による対応を求められることはありません。 このグリーンクレーム指令には、どのような環境主張を行う際に、どのようなガイドラインに従えばよいかについても具体的に記載されています。たとえば、製品を環境に配慮して使う方法について、消費者が適切な行動をとれるような情報提供が必要ですし、将来にわたって環境性能を改善していく計画についても、期限を定めた目標として明示することが求められます。企業が提供する情報は常に正確で、消費者が容易にアクセスできる状態にしておかなければなりません。 この指令の最終的な合意は2025年6月に予定されており、法案成立後には各国が国内法に転換することが義務付けられます。なお、「指令(Directive)」は加盟各国が国内法で実施する必要がありますが、「規則(Regulation)」は加盟27か国すべてに直接適用される共通ルールとして機能します。 |
||
| ■法案を順守し、サステナブルな社会と企業の成長を実現 | ||
|
このように、サステナビリティに関連するEU政策は、報告義務やデューデリジェンス(企業の人権・環境配慮の義務)にとどまらず、製品レベルでの具体的な対応まで含まれており、バリューチェーン全体に対して影響を与えるようになっています。 現在も政策の方向性をめぐってさまざまな政治的議論が交わされていますが、サステナビリティは今後もEU政策の最重要課題として位置付けられ、政策判断の原動力であり続けるでしょう。繊維業界においても注目度は高く、今後さらに規制が導入される見込みです。しかしこれは制約ではなく、私たち業界にとっては大きなチャンスでもあります。なぜなら規制に対して積極的に取り組むことにより、持続可能な社会の実現に貢献すると同時に、競争優位性の確立や新たなビジネスチャンスの創出につながるからです。特に繊維業界やコットン業界では、環境負荷の大きさや複雑なサプライチェーン構造が課題であり、これらの政策を無視することはもはや不可能です。今後もEUの動向を注視しながら、規制対応を通じて事業の持続的な成長を図ることが必要となるでしょう。 |
||
| ‖‖‖マルタ・ボンベーリ氏の講演詳細はこちら‖‖‖ | ||
| ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー | ||
| マルタ・ボンベーリ氏《ヒルアンドノウルトン アカウント・ディレクター》 ベルギー・ブリュッセルを拠点に、循環経済を始め、繊維、化学物質、先端材料、再生可能エネルギーなどの分野におけるEU政策を専門に活動。特に、繊維や化学物質の持続可能性をめぐるEU環境政策において専門的な知見を有し、クライアントに対してグリーンクレーム対応や製品表示、デューデリジェンス支援を行う。また、米国商工会議所EU支部では、グリーンクレーム指令に関する業務を主導。複雑化するEU規制の中で、企業が課題を乗り越え、ビジネスチャンスを最大限に活用するための政策分析や戦略立案にも取り組んでいる。 |
| 特別講演 | ||
| 「トランプ政権の日本企業への影響」 | ||
明星大学教授 細川昌彦 氏
|
||
| ▼▼▼▼▼▼ | ||
| ■なぜトランプ大統領の発言はコロコロと変わるのか? | ||
|
連日、トランプ大統領の発言が報道で取り上げられており、その言動は世界経済に大きな影響を与えています。日本に与える影響も大きく、多くの企業がトランプ大統領のコロコロと変わる発言に振り回されているように感じます。 トランプ大統領の発言はコロコロと変わるため、その政策は一貫性を欠いているように見えますが、実はその根本的な構造は非常に明快です。トランプ大統領の政策には、過激な意見を持つナバロ上級顧問、交渉の調整役であるラトニック商務長官とグリアUSTR(米通商代表部)代表、市場や金融の安定を見守る役割のベッセント財務長官の4人のブレーンが関わっており、トランプ大統領はその時々の政治的・経済的な状況に応じて、これら4人の意見のうち誰を採用するかを本能的に選んでいます。そのため、ある時は強硬な発言をし、別の時には一転して穏やかな対応を見せるといった政策運営の背景には、実は意図的な「役割分担」があり、どの人物の意見が反映されているかを知れば、トランプ大統領の発言の意味がとてもわかりやすくなります。 さて、今、日本とアメリカの間で関税交渉が行われていますが、現在はベッセント財務長官が中心に動いている状況です。これは、株価が急落し市場が混乱している状況を改善し、マーケットの安定を優先させたいという意図が表れています。ただし、この状況がずっと続くわけではなく、もし、ナバロ上級顧問の意見が採用された場合、状況は一変するでしょう。このように、4人のブレーンの誰が政策に関わっているのかを知ることで、今後の政策がどの方向に動くのかを予想することが可能です。 |
||
| ■今、関税を引き上げている理由とは? | ||
|
次に、なぜトランプ政権は関税を引き上げているのかを説明します。 そのため、関税交渉や経済政策を読み解く際には、トランプ政権の背後にある目的とその戦術を慎重に分析する必要があります。トランプ大統領が用いる言動の変化は、単なる気まぐれではなく、特定の成果を目指した計算された行動であることが多いのです。 関税を引き上げる目的は3つあり、まず1つ目はアメリカの貿易赤字を減らすため、2つ目はアメリカ国内の製造業を回復させるため、そして3つめは関税を交渉の道具として使うためです。 第一期トランプ政権時は貿易赤字の是正が関税を引き上げる主な目的でしたが、第二期トランプ政権では2つ目に挙げた「製造業の回復」が非常に重要視されており、関税によって輸入品の価格競争力を下げることで、国内製造業への投資を促し、産業の復活を目指しています。 そのため、日本との交渉でも「日本の企業がアメリカに工場を建てて雇用を創出したり、地域経済の活性化や税収の増加に貢献していることを示せば、関税をかける必要はない」と訴えています。 3つ目の「関税を交渉の道具として使う」というのは、関税を「脅し」や「カード」として使い、より優位に交渉を行うという意味で、関税引き上げをちらつかせつつ、農産物やエネルギーの輸入拡大を要求するといった交渉が度々行われています。よって、日本がアメリカにとって価値のある提案を提示することで、関税が緩和されたり撤廃されたりする可能性があるのです。 こうした背景を踏まえると、私たちにとって重要なのは、関税そのものではなく、その「背後にある目的」を正しく理解することです。目的が見えれば、それに応じた戦略的対応も可能になります。 |
||
| ■トランプ大統領が描く、中間選挙に勝利するためのシナリオとは? | ||
|
トランプ大統領が政策を決定する際に最も重視しているのは「選挙」です。来年11月にはアメリカの中間選挙があり、そこで勝利できるかどうかは、トランプ大統領自身の政治的影響力を左右する極めて重要なポイントです。 そのため、中間選挙に勝つために「株価が上がり景気が良くなる」状況を作り、「日本や中国からこれだけ譲歩を引き出した」と成果をアピールできるよう、今からシナリオを描いています。つまり今は交渉の成果を選挙活動に活かすための準備期間であり、市場を混乱させている関税政策も、景気回復をより印象づけるための政治的策略なのです。 このようにトランプ政権の動きを理解する上で、周囲のキーパーソンと目的、そして選挙スケジュールを押さえることが重要です。こうした点を意識して報道に接すると、「誰が発言しているのか」「今、トランプ大統領が思い描いているシナリオのどの段階なのか」によって、その発言の背景や意図が読み取れるようになります。そしてそれが、複雑に見える国際経済の動きを理解する手がかりにもなるのです。 |
||
| ■関税による日本への影響は? | ||
|
現在、アメリカが日本に対して課している関税の中で最も重要なのが自動車に対するものです。特に、自動車には25%という高い関税がかかっており、これは日本経済に大きな影響を与えています。なぜなら、日本からアメリカへの輸出で最も大きな割合を占めるのが自動車関連だからです。輸出が減少すれば国内の生産も落ち込み、結果として工場の稼働停止や雇用の減少につながります。現在、日本国内で自動車産業に従事している人は約550万人にものぼり、この分野への打撃は経済全体に大きな影響を及ぼします。そのため、日本政府が最も重点を置いて交渉しているのが、この自動車関税の撤廃です。 しかし、この交渉は単なる理屈では進みません。政策決定はすべてトランプ大統領の考え一つで決まるため、どれだけ筋の通った説明をしても、彼が納得しなければ前に進まないという難しさがあります。例えばトランプ大統領は、「日本はアメリカ車を差別している」といった主張を続けています。彼は日本の車両検査が厳しすぎるという誤解を抱いており、ボーリング玉を高所から落とすテストの検査を例に挙げて非難してきました。しかし、実際にはその検査方法は国連で定められた国際基準に沿ったもので、アメリカ以外の多くの国が採用しています。しかもトランプ大統領は『ボーリング玉を落としてへこまなければ検査合格』と勘違いしておりますが、実際は衝突時の乗客への衝撃を緩和できるようきちんとへこむかをテストしているのです。つまり検査基準自体を誤解しているですが、何度説明してもトランプ大統領の認識は変わらず、交渉には苦労しています。 また、コメの問題もトランプ大統領にとって重要です。現在、日本は30年前のウルグアイ・ラウンド交渉で合意した「ミニマム・アクセス米」という制度のもと、年間約77万トンのコメを無税で輸入しており、その約45%はアメリカから輸入しています。トランプ大統領は無税もしくは低関税でのさらなる輸入を求めていますが、国内の農業関係者や与党内からの強い反発があり、政治的に難しい状況です。しかしながら、日本では現在コメの供給不足が起きており、価格も上昇している現実を考えると、輸入量の拡大は国民生活にもプラスになる可能性があります。特に今後は日本米の輸出目標も立てられており、コメを輸出しながら輸入量を拡大するという柔軟な姿勢が求められていると言えます。 さらに、もう一つの重要なテーマは造船業です。造船業の核心は、鉄の溶接技術や鉄材を精密に加工する技術といった地道な技能であり、日本はこうした熟練技術を持つ人材を有していることで世界をリードしていましたが、現在では中国や韓国に追い抜かれ、日本の存在感は大きく低下しています。アメリカに至っては、以前は技能者を移民で補っていましたが、アメリカ国民の雇用を促進するために移民の雇用を減らした結果、技能者不足となり、もはや軍艦すら自国で製造できず海軍力の低下が安全保障上の重大な懸念となっています。そのため、アメリカは日本や韓国に対し、造船支援の協力を求めていますが、日本の造船業も低迷し、アメリカへの支援を行える余裕がないため、今後は日本政府が造船業に対し支援を行うことでアメリカからの要請に応えられるように動くのではないかと予測しています。 このように、日本にとってアメリカとの関税交渉は、自動車・コメ・造船という三つの柱を中心に展開されており、それぞれが経済や安全保障、そして国民生活にも直結する極めて重要なテーマとなっています。現実の国際交渉では、論理よりも相手国のリーダーの意向や国内政治事情が大きく関わってくるため、日本としては粘り強く、かつ戦略的に対応していくことが求められています。 |
||
| ■『対岸の火事』ではすまされない米中関係に注目 | ||
|
最後に、米中関係について一言申し上げます。今週末からスイスで米中の貿易交渉が始まりますが、現在の関税状況は非常に深刻です。アメリカは対中輸入品に145%もの関税をかけており、中国もアメリカ製品に対して125%の関税を課しています。どちらも100%を超えており、これは正常な貿易が成立しないレベルの関税です。しかしこの状態は長くは続かないだろうと、今回の米中貿易交渉を担当するアメリカのイエレン財務長官も認識しています。なぜなら、今回の関税は特定の品目に限らず、「あらゆる中国製品」にまとめて課されているため、市場の大半を中国からの輸入品が占める衣料品やおもちゃなどが手に入らなくなる状態を引き起こすからです。そうなると、国民の不満が一気に高まり、「トランプ政権は一体何をやっているのか」と批判が集中し、支持率を大幅に下げる要因となるため、今回の交渉では特に、おもちゃや衣料品など、国民生活に直結する品目から優先的に関税が下げられていくと予想されます。しかし、全撤廃は難しいため、アメリカ市場が減少した分、中国製品はアジア諸国に洪水のように流れ込む可能性があります。実際、東南アジア諸国やEUなどはすでに「セーフガード(自国の産業が打撃を受ける場合に、一時的に輸入を制限する措置)」や「アンチダンピング(不当に安い価格で輸出してくる場合に、特別な関税を上乗せする措置)」などの対策を取り始めていますが、日本はこれらの対応が遅れている印象です。 これから先、日本にも確実に米中の関税問題の余波が押し寄せてくるでしょう。今後はただ単に「中国を刺激したくない」といった外交姿勢だけでは不十分であり、日本も将来を見据えて、今のうちから体制を整えて守りを固める準備が必要です。 今日お話ししたことは、ビジネスチャンスとしての視点を持つこと、そしてこれから先のシナリオを読み解く力を身につけることの重要性を示しています。同時に、米中関係の変化に対して早めに備えることは、繊維アパレル業界はもちろん、多くの業界にとって欠かせない課題です。 |
||
| ‖‖‖細川昌彦氏の講演詳細はこちら‖‖‖ | ||
| ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー | ||
| 細川昌彦氏 《明星大学教授》 経済産業省で約30年にわたり勤務し、そのうち10年間は日米間の経済交渉、特に鉄鋼分野の交渉をはじめとした通商問題を担当。現在は明星大学で教鞭をとりながら、企業支援やメディア出演を通じて情報発信を行う。著書『トランプ2.0 米中冷戦時代の到来』では、トランプ大統領再選後の影響について論じている。 |
| 講演 | ||
| 「データに基づくアメリカ綿の持続可能性」 | ||
| CCI国際綿花評議会 上席理事 ラズヴァン・ワンチャ 氏
|
||
| ▼▼▼▼▼▼ | ||
| ■持続可能な未来を築く「7世代先の原則」 | ||
|
皆さん、「7世代先の原則」という言葉を聞いたことがありますか?これは、ネイティブアメリカンの教えに由来する非常に深い哲学であり、自分たちの行動や決定が7世代先、つまり約200年後の未来にどんな影響を与えるかを考えて判断しなければならないという思想です。 実は、アメリカ建国の父であるベンジャミン・フランクリンもこの「7世代先の原則」に感銘を受け、アメリカ合衆国憲法の理念に取り入れたと言われています。この思想は、今日のアメリカの政府機関や日々の活動にも根付いており、世代を超えた持続可能な考え方の基礎となっています。 私自身も実際にこの哲学が社会の中に根付いている様子や関連する様々なデータを目にしてきました。本日はデータ主導型のサステナビリティ、特にアメリカ綿花産業におけるサステナビリティへの取り組みについてお話しし、サステナブルなサプライチェーンで価値を生み出すために「データをどう使えばよいか」や「プロセスを改善し、より良い結果につなげるためにはどう活用していけばよいか」を共有したいと思います。 |
||
| ■データを収集・活用することでサステナビリティと収穫量アップを実現 | ||
|
私たちが活用しているのは『U.S.コットン・トラスト・プロトコル』と呼ばれるシステムです。これは簡単に言うと、アメリカ産綿花におけるサステナビリティとトレーサビリティを数値化・可視化するためのシステムで、スタートしてから約4年が経った今では多くの農家が参加し、認証プログラムとしても機能しています。 このシステムには2つのプラットフォームがあり、1つは「プロトコル・プラットフォーム」と呼ばれ、農業におけるサステナビリティを測るためのデータの集計・分析を行っています。もう1つは集められたデータを農家やブランドに提供し、サステナブルな取り組みをサポートする「透明なサプライチェーン」です。 土壌の状態は農家にとってはもちろん、サステナビリティにとっても非常に重視すべき要素です。そこでU.S.コットン・トラスト・プロトコルではプログラムに参加いただいている農家の方々からデータを収集し、アメリカの綿花栽培面積の約31%にあたる約200万エーカー分のデータを収集しています。 データ収集は「コットンベルト」と呼ばれる綿花栽培地域の319の郡で行われており、年間約200万件以上のデータが集められ、現在では累計で約1,000万件以上のデータが蓄積されています。これらのデータは、U.S.コットン・トラスト・プロトコルが設定した6つの環境目標に大いに貢献しており、いくつかの目標はすでに達成し、その他の進捗状況も順調です。 もちろん課題もあり、最大の課題は「気候」です。現在アメリカの綿花栽培地の約47%が干ばつの影響を受けており、さらに洪水、台風、気温変動なども土壌に影響を及ぼしています。そのため進捗状況は単年のデータではなく3年間の平均値を採用し、気候変動などの年ごとの変動に左右されず、長期的なトレンドを把握できるようにしています。このようにデータに基づくサステナビリティへの取り組みは着実に成果へとつながり、U.S.コットン・トラスト・プロトコルに参加している農家の収量(1エーカーあたりの収穫量)は、全国平均を上回っているという結果が出ています。 |
||
| ■AIによるデータ分析で改善点ときめ細やかな対応方法を提案 | ||
|
U.S.コットン・トラスト・プロトコルでは6つの環境目標を設定していますが、今回は、2つのケーススタディをご紹介します。 1つ目は「温室効果ガスの削減」についてです。2015年には綿花1ポンドあたり2.4kgだったCO₂排出量は、2023年には1.9kgに減少し、2025年の目標1.5 kgに向けてすでに29%の削減が達成されています。排出源を見ると、肥料や農薬の使用、農業機械の運転・乾燥処理などの工程が主な原因となっており、これらに焦点を当てて改善することでさらなる削減が見込まれます。 2つ目は「水の利用」についてです。アメリカの綿花の約3分の2は灌漑(人工的な水やり)を必要としていません。しかし、U.S.コットン・トラスト・プロトコルの参加農家のうち、約3分の1は灌漑が必要な地域にあります。さらに地域によってはより精密な灌漑が必要で、例えば、「乾燥しているが温暖な地域」では土壌侵食の管理が必要ですし、「湿潤な地域」では土壌水分の保持と活用が重要になります。 このようにそれぞれの地域に合った管理方法を選ぶため、U.S.コットン・トラスト・プロトコルでは気候・天候・土壌の水分量などのデータで活用し、AIや機械学習による分析を行うことでサステナブルな管理方法を提案しています。 |
||
| ■U.S.コットン・トラスト・プロトコルが推奨する再生型農業とは? | ||
|
私たちはよく「再生型農業とは何か」「U.S.コットン・トラスト・プロトコルではどのように再生型農業を実践しているのか」といった質問を受けます。再生型農業とは、土壌の攪乱を最小限に抑え、土壌中に生きた根を保ち、地表を常に被覆した状態にして作物や微生物の多様性を最大限に生かすという原則に基づいた農業です。場合によっては家畜も導入され、農場内の生物的循環を促進しています。 U.S.コットン・トラスト・プロトコルに参加する農家では、このような再生型農業の原則に基づいた取り組みが行われています。具体的には、不耕起農法を取り入れている農家が全体の約60%を占めており、被覆作物の利用は62%、輪作の実施は78%となっています。また、農薬の使用に関しても、必要最小限にとどめ、適切なタイミングで、適切な場所に、適切な量を使用するという精密な管理が行われており、87%の農家がこの方法を実践しています。栄養管理についても、化学肥料だけでなく自然由来の資材が積極的に活用されており、水源を保全するための対策も講じられています。 さらに、農家自身による自己評価制度も導入されており、120項目に及ぶ質問に回答することで、土壌の健全性、栄養管理、水管理、化学薬品の使用状況、生物多様性などの分野について、自らの取り組みを振り返る仕組みになっています。 それでは再生型農業が土壌の健全性にどのような影響を与えているのか具体的なデータを見てみましょう。例えば、不耕起農法では作物の根や残渣(ざんさ)を地表に残すことで、土壌の物理的・生物的な構造が保たれます。残留物が15%以下である場合は、従来型の農法とされますが、残留物を多く残す農法では、土壌の健全性が大きく改善されていることが確認されています。実際、10年以上従来型農法を続けている農場では、土壌の改良度がマイナス0.5であるのに対し、不耕起農法を実践している農場ではプラスの値を示しています。 また、土壌の侵食についても明確な違いがあります。不耕起農法の農場では、1年間における土壌侵食量は1.8トンにとどまっているのに対し、従来型農法ではその約4倍となる7.2トンもの侵食が確認されています。これは、不耕起や被覆作物の利用によって、土壌の表面が守られていることを示すデータです。 |
||
| ■データ主導型サステナビリティの重要性は今後ますます拡大傾向 | ||
|
U.S.コットン・トラスト・プロトコルとは別に、「クライメート・スマート・コットン・プログラム」と呼ばれる新たな取り組みも進められています。これは、新規の農家も含めて持続可能な農業を実践することを目的とした共同イニシアチブで、収益性や農業運営、環境保全の向上を目指しています。このプログラムの下で生産されている綿花は、年間で約9,100万ベールに達しています。2023年から2024年にかけては、ブランドや小売業者によっておよそ1億1,000万単位の綿花がトラッキングされました。ブランド側が保有するシステムによって、製品の流通過程が追跡可能になっており、トレーサビリティを確保した製品の数も年々増加しています。 このような仕組みは、アメリカ国内の法規制のみならず、EUの「グリーンディール」などの国際的な規制にも準拠できるよう設計されており、法令遵守とサステナビリティの両立を可能にしています。こうした取り組みの結果、私たちは昨年度において、設定した目標の60〜70%を達成することができました。今後もこの動きはさらに拡大していく見込みです。 今回ご紹介してきたように、U.S.コットン・トラスト・プロトコルでは、信頼性の高いデータを基盤として、環境負荷の低減や生産性の向上、そしてサプライチェーン全体の透明性の確保に取り組んでいます。近年では、こうしたサステナビリティに関連するデータがサプライチェーン全体で活用されるようになっており、企業はそれを効率的に活用することで、自社の取り組みを可視化し、さまざまなルールや規制への対応を可能にしています。アメリカやEUにおいても、サステナビリティは企業の重要なセールスポイントとなりつつあり、その傾向は今後ますます強まると考えられます。私たちは、こうした取り組みが「7世代先の未来」へとつながっていくことを確信しています。 U.S.コットン・トラスト・プロトコルが保有しているデータの大部分は、公式ウェブサイトに掲載されており、年次報告書として公開されています。そこには一般的な情報だけでなく、加盟メンバー向けに提供される詳細なデータも含まれていますので、ぜひU.S.コットン・トラスト・プロトコルにご参加いただき、共にサステナブルな未来を築いていければと願っております。 |
||
| ‖‖‖ラズヴァン・ワンチャ氏の講演詳細はこちら‖‖‖ | ||
| ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー | ||
| ラズヴァン・ワンチャ氏 《国際綿花評議会(CCI)上席理事》 テキスタイルの学位とMBAを取得後、複数の企業でマーケティングや事業開発に従事し、繊維業界で豊富な実績を積む。現在は、持続可能な綿花製品の普及とトレーサビリティ強化を推進するCCIにおいて、アジア地域、特にインドネシアを含む供給網整備を担当。サステナビリティとトレーサビリティの両立を重視し、その二本柱を軸としたCCI の取り組みを牽引している。ジャカルタでの業界向けイベントでは「景気後退時にも品質と透明性を堅持する」と明言し、多くの支持を獲得した。 |
| ゆうちゃみさんに「COTTON AWARD 2025」を授与 | ||||
|
||||
|
「COTTON AWARD 2025」の授与式が開催され、コットンの日のイベントのラストを華やかに飾りました。 「COTTON AWARD」はコットンの持つ優しさ、さわやかさ、ナチュラルさなどのイメージにふさわしい著名人に贈られる賞で、今年の受賞者に選ばれたのは、モデル・タレントとして多方面で活躍するゆうちゃみさんです。 ゆうちゃみさんは、2023年4月まで雑誌『egg』の専属モデルを務めたほか、バラエティ番組やドラマ、CMなどにも数多く出演し、2022年には「ブレイクタレント(女性部門)」で第1位に輝くなど、その勢いはとどまるところを知りません。さらに、2024年10月には歌手デビューも果たし、地元・東大阪市では魅力PR大使としても活躍中。その他にも2025年大阪・関西万博のスペシャルサポーターに就任するなど、令和のマルチタレントとして注目を集めています。 今回の受賞は、そんなゆうちゃみさんの明るく飾らないキャラクターと、自然体で親しみやすい存在感が、コットンの持つイメージと重なることから選出に至りました。 日本紡績協会の尻家会長よりオーナメントを授与されたゆうちゃみさんは、「こんな素敵な賞をいただけて、本当に光栄です。『私でいいの?』と驚きましたが、とても嬉しいです。」と、受賞の喜びを語りました。 コットン素材の真っ赤なワンピースと輝くような笑顔で授賞式に花を添えたゆうちゃみさんは、「コットンは着心地も良くて、肌触りも大好き。乾燥肌の私にとっては静電気が起きにくいところも嬉しいです。普段からよく着ていますし、コットンは私にとって“第2のママ”のような存在。夏になると家族で一緒に使っていたコットンの布団を思い出します。あたたかくて包み込んでくれる感じが大好きです!」と、コットンへの深い愛着を語りました。 また、「コットンは日常生活の中に自然と溶け込んでいて、衣類だけでなく、寝具やタオル、メイク用品など、暮らしの中でいつもそばにある素材。みんなに愛される“人気者”なんだなと思います」と笑顔でコメント。会場を和ませる関西弁と明るいトークで、終始あたたかな雰囲気に包まれた授賞式となりました。 |
||||
| ‖‖‖「COTTON AWARD 2025」の授与式の模様はこちら‖‖‖ | ||||
| ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー | ||||
| ゆうちゃみさん 2001年生まれ、大阪府出身。ファッション雑誌『プチレモン』『Popteen』『egg』の専属モデルを経て、幅広いメディアで活躍。バラエティ番組やドラマ、CMに加え、YouTubeチャンネルの運営やアーティスト活動も展開中。2024年には歌手デビューを果たし、2025年には大阪・関西万博のスペシャルサポーターに就任。明るい関西弁と親しみやすいキャラクターで、Z世代を中心に絶大な人気を誇る新世代タレント。 |
||||
| ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー | ||||
| ‖‖‖過去のアワードの受賞者はこちら‖‖‖ | ||||
| ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー |
| レセプション | ||||
|
||||
| 第二部のレセプションでは日米の綿業界の皆様にご参加いただき、和やかな雰囲気の中で親交を深めるとともに、意見交換や質問などが行われ、成長の種がまかれるような意義深いひとときとなりました。 |
一般財団法人 日本綿業振興会(Japan Cotton Promotion Institute)
Copyright(c) 2024, JCPI. All rights reserved.